Section1
オリヒメは新しいタイプのロボットです。
このロボットは、遠隔地にいる人のアバターとして機能します。
オリヒメを使えば、ロボットの近くにいる人と会話することができます。
また、ロボットの頭や手を自由に操作することで、さまざまな感情を表現することができます。
オリヒメは身長23cmで、内部にカメラ、マイク、スピーカーが搭載されています。
インターネットを通じてパソコンで操作することができます。
身体障害者でも、特殊なアイトラッキングシステムを使えば、ロボットを操作することができます。
オリヒメは、さまざまな理由で特定の場所にいることができない人のために開発されました。
教室や商談、家族のイベントなど、さまざまな場面で活躍します。
| avatar | (名)〔コンピュータ〕アバター |
|---|---|
| robot | (名)ロボット,人造人間 |
| function | (名)機能,働き,作用,目的 |
| remote | (形) (距離的に)遠い,遠方の; 遠隔の; 人里離れた,へんぴな |
| control | (名)支配(すること), 取り締まり,管理,監督,管制 |
| freely | (副)自由に,勝手に |
| centimeter | (名)センチメートル |
| microphone | (名)マイクロフォン,マイク |
| physically | (副)肉体的に,身体上 |
| tracking | (名)追跡 |
| system | (名)(政治・経済・社会などの)機構,制度 |
Section2
オリヒメは、吉藤健太郎によって作られました。
オリヒメのアイデアは、彼自身の体験から生まれたものです。
吉藤は幼い頃、3年半ほど学校に通うことができませんでした。
授業に出たいのに、出られない。
非常に寂しい想いをしました。
「アバターがあれば、学校に行かなくてもクラスメートと一緒にいられるのに」と思いました。
この頃、彼はロボットの設計に興味を持つようになりました。
吉藤は工業高校に入学しました。
18歳の時、アメリカで開催されたエンジニアリングコンテストに参加しました。
そこでさまざまな人と出会い、「人とうまくコミュニケーションがとれない人を助けたい」という目標を見つけました。
だから、彼は自分のことを「ロボットエンジニア」ではなく、「ロボットコミュニケーター」と呼んでいます。
| attend | (動)〈会などに〉出席する; 〈儀式に〉参列する |
|---|---|
| extremely | (副)極端に,きわめて |
| lonely | (形)孤独な,ひとりぼっちの |
| period | (名)期間 |
| design | (動)〈絵画などの〉下図[図案]を作る; 〈建築・衣服などを〉デザインする,設計する |
| engineering | (名)工学; 機関学 |
| contest | (名)(勝利または賞を目ざしての)競争; 競技,競演,コンテスト,コンクール |
| communicator | (名)コミュニケーター; 通信機 |
Section3
吉藤は、オリヒメを完成させても、決して満足することははありませんでした。
「オリヒメがもっと多くの人の役に立てば」と考えました。
そこで、「オリヒメ-D」の開発を始めました。
基本的にはオリヒメと同じ機能です。
しかし、動き回ったり、物を運んだりすることができ、身長は約120センチです。
2018年、オリヒメ-Dは東京のロボットカフェで初めて使用されました。
ロボットを操作したのは、遠隔地にいる身体障がい者の方々です。
オリヒメ-Dを通じて、飲み物を運んだり、お客さんとコミュニケーションをとったりしました。
ロボットを使うことで、障がいのある人は働く喜びを感じることができました。
つまり、社会参加をしているという実感を持つことができたのです。
| successfully | (副)首尾よく,うまく; 幸運に(も) |
|---|---|
| basically | (副)基本原理として; 基本的に |
| cafe | (名)(ヨーロッパなどの)料理店; カフェテラス |
| physical | (形)身体の,肉体の |
| disability | (名) (身体などの)不利な条件,障害,ハンディキャップ |
| customer | (名)顧客; 得意先,取引先 |
| joy | (名)喜び,うれしさ |
| participate | (動)〔人と〕〔…に〕参加する,あずかる,関係する |
Section4
オリヒメが役立つのは、体が不自由な人たちだけではありません。
他の困難を抱えている方にも有効です。
たとえば、働く人の中には家にいなければならない人もいます。
彼らは幼い子どもや高齢の家族の世話をしなければならないのです。
オリヒメを使えば、まるで同じ職場にいるような感覚で、同僚と会話ができます。
また、さまざまな事情で学校に通えない生徒にも、オリヒメは役立っています。
オリヒメを使えば、友達と一緒にいるような感覚で過ごすことができます。
これこそ、吉藤が幼い頃に望んでいたことでした。
オリヒメのおかげで、人々は今までいられなかった場所に “いる “ことができるようになりました。
吉藤のロボットは、多くの人の生活を変え、未来に希望を与えているのです。
| elderly | (形)〈人が〉かなり年配の,初老の |
|---|---|
| coworker | (名)(一緒に仕事をする)協力者 |
| workplace | (名)仕事[作業]場 |
| exactly | (副)正確に,厳密に |
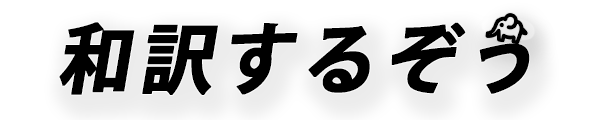
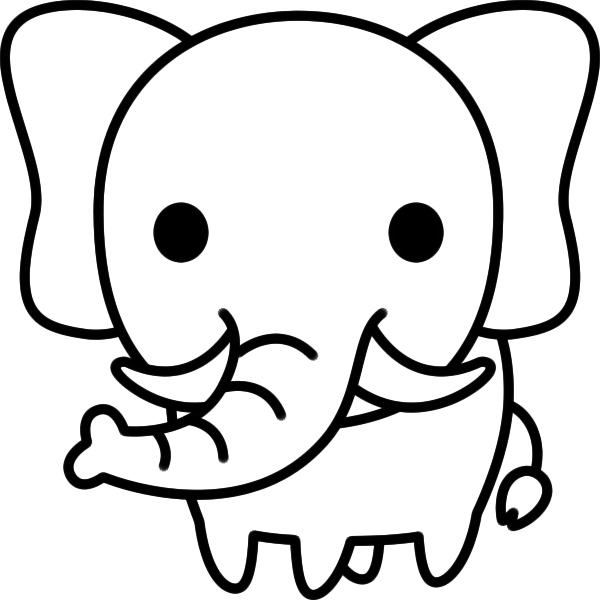
カテゴリー