Section1
人類は古来よりさまざまな病気に悩まされてきました。
克服されたものもありますが、他のものに関しては、治療法はまだ確立されていなものもあります。
天然痘、マラリア、コレラ、ペスト、脚気、インフルエンザなど、環境の変化やグローバリズムによって、世界各地から日本に持ち込まれた病気も多くあります。
その中でも結核は、長い間人間を苦しめてきました。
紀元前1000年頃のエジプトのミイラには結核の兆候が見られ、イエス・キリストの時代のエルサレムにもこの病気があったようでした。
日本では弥生時代の人骨から見つかりました。
1900年以降は、最も恐ろしい「不治の病」と呼ばれ、主要な死因の上位にランクされました。
しかし、アレクサンダー・フレミングによって結核の治療法が確立されたため、現在では克服されています。
| cure | (動)〈病気・病人を〉治す,いやす |
|---|---|
| smallpox | (名)天然痘,ほうそう |
| malaria | (名)マラリア |
| cholera | (名) コレラ |
| plague | (名)疫病,伝染病 |
| beriberi | (名) 脚気(かつけ) |
| influenza | (名) インフルエンザ,流行性感冒 |
| globalism | (名)グローバリズム |
| tuberculosis | (名)結核 |
| mummy | (名)ミイラ |
| Egypt | (名)エジプト |
| Jerusalem | (名)エルサレム |
| Jesus Christ | (名)イエス・キリスト |
| bone | (名)骨 |
| rank | (名)階級,等級,(社会的な)地位 |
| fearful | (形)恐ろしい,ぞっとするような,ものすごい |
| incurable | (形)不治の,治らない |
| overcome | (動)〈敵・悪癖・困難などに〉打ち勝つ,〈…を〉負かす; 〈…を〉征服する |
| Alexander Fleming | (名)サー・アレクサンダー・フレミング |
Section2
アレクサンダー・フレミングは細菌学者で、抗菌物質リゾチームを発見しました。
彼はペニシリンという抗生物質を発見しました。
ペニシリンには結核を治す効果があります。
この2つの発見は完全に偶然に起こりました。
リゾチームの場合、フレミングは細菌を塗ったシャーレにくしゃみをしました。
数日後、彼は細菌の周りの微生物が破壊されているのを発見しました。
リゾチームは 動物の唾液や卵白に含まれる殺菌作用のある酵素です。
現在では、食品添加物や医薬品として使用されています。
フレミングの研究室は散らかっていました。
彼は汚れたシャーレを捨てる準備をしていました。
その時、シャーレの中の青カビの縁の部分だけバクテリアの増殖が妨げられているのを発見しました。
この出来事がヒントになりました。
そして研究を続け、ついにペニシリンを発見したのです。
| bacteriologist | (名)細菌学者 |
|---|---|
| lysozyme | (名)ライソザイム; リソチーム; リゾチーム |
| antibacterial | (形)抗菌性の |
| antibiotic | (形) 抗生の |
| penicilin | (名)ペニシリン |
| sneeze | (名)くしゃみ |
| petri | (名)ペトリ |
| coat | (動)〈ほこりなどが〉〈…の〉表面をおおう |
| bacteria | (名)バクテリア,細菌 |
| microbe | (名)微生物; (特に)病原菌 |
| enzyme | (名)酵素 |
| sterilize | (動)〈…を〉殺菌[滅菌,消毒]する |
| property | (名) (ものの)特質,特性 |
| saliva | (名)唾液(だえき), つば |
| additive | (名) (食品・ガソリンなどの)添加物,添加剤 |
| messy | (形)取り散らかした,乱雑な |
| mold | (名)かび; 糸状菌 |
| incident | (名)出来事 |
| clue | (名)〔なぞを解く〕手がかり; 〔調査・研究などの〕糸口 |
Section3
フレミングによって発見されたペニシリンは、多くの感染症を治癒可能にしました。
ペニシリンの実用化は、私たちの生活に大きな変化をもたらしました。
その後、ワクチンの開発が進み、感染者の数は急速に減少しました。
ある日、農夫が川で溺れていた少年を助けました。
少年の父親は農夫の善意に深く感動し、医者になるための息子の学費を支払いました。
実は、農夫の息子はアレクサンダー・フレミングで、川で溺れていた少年はウィンストン・チャーチルでした。
1943年、イギリスの首相だったチャーチルは肺炎を患っていましたが、ペニシリンで完治しました。
フレミングがチャーチルを二度も救ったという話は世界中に広まりました。
しかし、これは単なる都市伝説でした。
| infectious | (形)a〈病気が〉伝染性の |
|---|---|
| curable | (形)治癒(ちゆ)できる,治せる,治る |
| progression | (名)(段階的な)前進,漸進(ぜんしん); 発達,進歩 |
| vaccine | (名)痘苗(とうびよう); ワクチン |
| decrease | (動)減少する; 低下する; 〈力などが〉衰える |
| goodness | (名)(生来備えている)徳,善性,優しさ |
| tuition | (名)授業料,月謝 |
| prime | (形)優良の,最良の,第一等の; すばらしい,極上の |
| minister | (名)(英国・日本などの)大臣 |
| pneumonia | (名)肺炎 |
| urban | (形)都市の,都会の,都市特有の |
| legend | (名)伝説,言い伝え |
Section4
生物に存在する成分のひとつであるタンパク質の分析は、長い間不可能とされてきました。
化学者であり技術者であった田中耕一は、試験的な方法を研究し続けていました。
ある日、彼は試験液に誤ってアルコール性の「グリセリン」を入れてしまいました。
彼はその液体を捨てようとしました。
「これをあえて実験に使いました」と彼は言いました。
すると突然、タンパク質を表す波が現れました。
彼は目を輝かせてそれを見つめました。
この発見によって、多くの病気の原因が解明され、その結果、医学の進歩に役立ったのです。
単なる偶然や小さなミスが、人を素晴らしい成功へと導くことがあります。
たとえ役に立たないと思われるようなことでも、研究を続けることが大切なのです。
研究し続けるモチベーションが、彼らに成功をもたらしたのです。
| analyze | (動)〈ものを〉分析する,分解する |
|---|---|
| protein | (名)たんぱく質 |
| component | (形)構成している,成分の |
| tentative | (形)試験的な,仮の |
| alcoholic | (形)アルコール(性)の,アルコール入りの |
| glycerin | (名) グリセリン |
| liquid | (名)液体 |
| dare | (助)あえて…する,思い切って[恐れずに,生意気にも]…する |
| represent | (動)〈…を〉表わす,示す,象徴する; 意味する |
| gaze | (動)(熱心にじっと)見つめる,熟視する |
| mere | (形) ほんの,単なる,まったく…にすぎない |
| motivation | (名)〈…する〉動機(づけ), 刺激,やる気 |
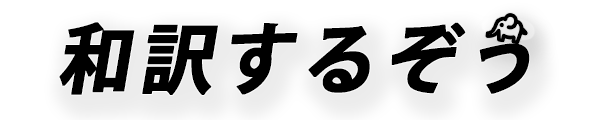
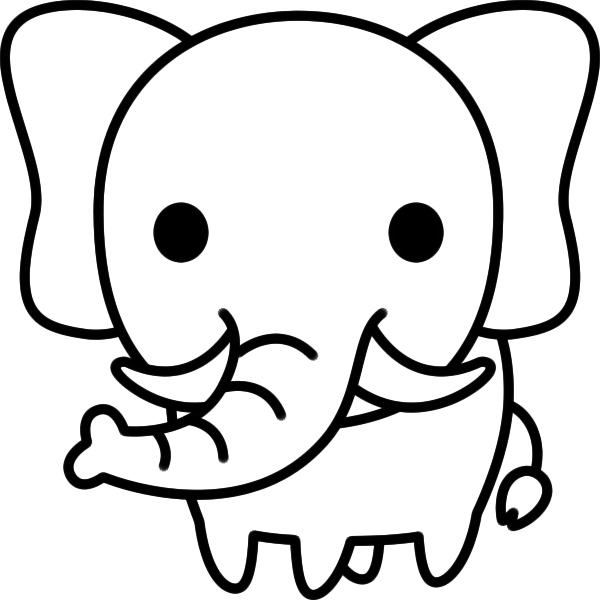
カテゴリー